
でこぼこ道やおおまたで歩くために行った座る練習をご紹介します。
座る練習??と思うかもしれません。
まずは立つ練習の前に座ってバランストレーニングを行うことが大切です。
今回は椅子とバランスボールに座って行ったトレーニングをご紹介します。
バランストレーニングが大事
ギランバレー症候群患者さんはでこぼこ道を歩いたりや小走りが苦手という話しをしましたが、今回はその続きになります。
前回??という方はこちら↓をご覧ください。
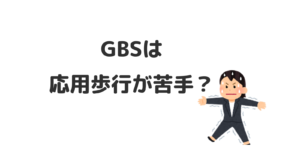
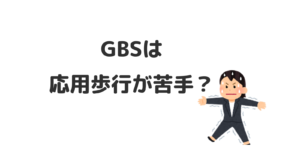
今回も医療スタッフ向けの内容となります。
専門用語が多くなりますが、あらかじめご了承ください。
でこぼこ道を歩いたり、ジャンプや小走りするためには、どんな姿勢や動作でも転ばないようにコントロールできるバランス能力が必要です。
ですので最初は座った状態で、転ばないようにキープする練習を行いました。
バランストレーニングの経過は
3、4か月目 座位(静的→動的+ボールエクササイズ)
4、5か月目 立位(静的、+殿筋群個別トレーニング →動的)
最後 ステップ、プライオメトリクス へ
という感じです。
まずは青竹を踏んだ状態で椅子に座る
え??青竹と思った方、いらっしゃるかもしれません。
私の場合、足底感覚が鈍かったことや足裏のしびれがひどかったので感覚のリハビリとして、青竹ふみを行ったんです。
その時の話はこちら↓になります。
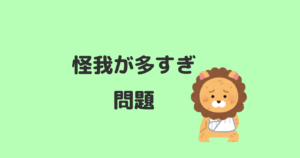
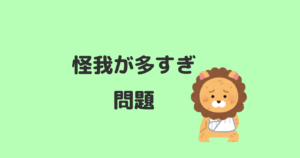
いきなり足踏みはしませんでした。というかできませんでした。。。
まずはただ足元に青竹を置いて、椅子に座るトレーニングから始めました。
細かい方法を書くと永遠に書き終えない気がしますので。。。。
最も大切なことは
体幹をアップライト(=背筋を起こす)を保ちながら座ることです。
このころは自宅にいて何とか生活している感じでしたが。。
ちょっと足元が平らでなくなるだけでも、思った以上にできていませんでした。
上記のポイント
ポイント①青竹を踏んでいることを意識する
突起部から得られる感覚と視覚的情報をひたすら確認してました。
例 踵を強く踏む ⇒青竹のでこぼこ部分の圧情報が得られる⇒目で確認する
普通ならなんてことないものだと思いますが、それでも最初はアロディニアがあって痛かったり
ちょっと圧刺激を弱めると踏んでいるのかわかりにくかったんです。苦笑
強さや足で踏む場所を変化させ、その都度目で確認しながら足裏からの情報を知覚できるように練習しました。
足裏からの情報が増えると、バランス機能がアップします。
ただ座った状態で足裏の感覚を意識することから始めました。
ポイント②体幹の安定化を図る
バランスアップするには、足裏から地面の情報を得ることとともに、体幹の安定が大切です。
ところが私の場合、呼吸筋や体幹筋のダメージが大きく
急性期は自分の頭の重さを支える力もない状況でした。
ですので座る練習をしながら、体幹のトレーニングも行いました。
何をしたかというと、座った状態でブレーシングです。
ブレーシングすることによって、より大くの体幹筋を使うようにしてました。
それでも最初は全然無理で。。。
まずはべこっと上がったままの横隔膜と胸郭の可動性を高めるところからでした。
その後呼吸機能の改善も兼ねて、息を吸いしっかりと体幹を起こして座るようにしました。
ポイント③余分な力を入れないように意識する
最初は座っているだけでも、なんとなくふらつくので力が入っていました。
また回復した筋、してない筋、しびれ等々の問題があるため
まっすぐ座るということがうまくできません。
鏡で姿勢を見ながら、無理な力をいれずに楽に座る(代償と過剰努力×へ)
できたら、青竹ふみという感じで動的トレーニングに移行しました。
バランスボールのトレーニング
ある程度座れるようになってから、バランスボールに乗って座る練習をしました。
おそらく皆さんがイメージするダイナミックなものではなく、非常に地味なものになります。
基本は青竹を踏みながら座る練習(上記ポイントと同じです)
その頃の様子はこちらになります。


座った状態で動く練習
座わるだけから、すこしづつ動かすようにしました。
どんな感じかというと
ボールにのってブレーシングしたあと、ゆっくりと片足あげです。
その際
体幹が崩れないようにする
ボールがあまりゆれないようにする
支持足のほうはショートフットエクササイズを行う
など
テーマを決めて鏡で姿勢を確認しながらボールに乗っていました。
大きな動きのトレーニングでというと・・・
バランスボールに乗って片足上げたまま、片足でボールを前後に動かす です。
その時も大きく動かすのではなく、足底感覚や座面の変化を意識しながら、
身体重心を支持基底面内でコントロールする事を重視してました。
たまにボールにのって跳ねたりしていましたが、
傍目からみるとただボールに座っているだけという。。。
非常に地味なもの
これを1か月ぐらい続けてました…
最後に
次の1か月の立位も似たような地味なバランストレーニングでした。
何が言いたいかというと、バランストレーニングといっても
ステップエクササイズや応用歩行といった
大きな重心移動を伴うものではなく
いかに感覚入力を高め、姿勢をキープする力を得ていくかに、ポイントを絞っていました。
